炒檳城老鼠粉 penang fried rat noodle [ペナン風米粉マカロニ炒め]
![炒檳城老鼠粉 penang fried rat noodle [ペナン風マカロニ]の麺](https://w-foods.com/wp-content/uploads/2012/05/P1010897wp.jpg)
檳城はマレーシア西部のペナン島のこと。老鼠lao shuはネズミ、粉fenは文字通り粉末のことだが、特に米を原料とした加工品の名称に使われます。米粉を練って作った麺で太さは日本のうどん(讃岐うどんや伊勢うどん)に近いのですが、長さは3~4センチほど。それもまな板の上を手のひらで転がしながら作るとみえ、麺の両端が鼠のしっぽのように細長い形をしていることからネズミの名がつきました。
もちもちと弾力があり、小麦の麺とは違った食感が美味しいです。短くて極太なのでスープ麺より炒め麺がオススメです。
米粉を使った短いパスタ。食感が面白い!
これはもともと中国南部発祥の麺料理です。
かつての中国は北部は小麦、南部は米の文化と言われていました。
その米食文化の華南の人々が東南アジアに散っていったことで華人が居住するマレーシアやシンガポールの屋台街で目にします。
特にマラッカ海峡貿易の拠点として栄えたペナン島には華人が多く、ペナン島の屋台街には中国由来で、かつ労働者の日常食としての「早くて、安くて、うまい」ごはんが沢山あるのです。
米の澱粉質がむちむちとはじけるような弾力。
その麺に合わせているのがしゃきっとしたもやしと葱。
貝と干しエビでうまみをだし、仕上げにタップリとした胡椒がかかる。
全体に味つけが濃いめなのはやはり労働者の日常飯だったからでしょう。
ちなみになぜペナンを中国語で檳城bin chengと書きますがこれは表意語です。
ペナン島はマレー語で檳榔(びんろう)の島という意味を持つのです。
直訳すると「びんろう島のネズミのしっぽ麺」って感じ?
もちもちしていてコシのあるうどんや麺が好きな方はなかなかはまる味ですよ。
ジャランアローの屋台街
Jalan Alor, クアラルンプール
クアラルンプールの繁華街ブギ・ビンタン地区にある中華系屋台の集まる通り。立地がよいため、外国人観光客の姿も多い。
一見店舗のような形ですが、それぞれ経営が別の屋台が店を構えており、いろんな料理を楽しむことができます。
観光客が多いためメニューを揃えている店がほとんどで言葉ができなくても立ち寄りやすいし、夜遅くなっても店が開いているので助かる。ただし、観光客向けではない屋台の方がもっと安いです。
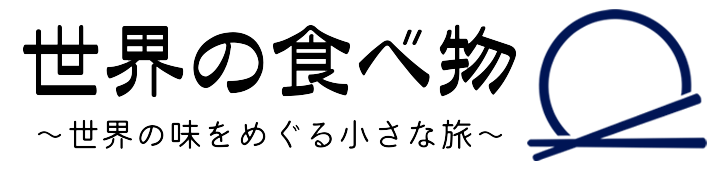
![炒檳城老鼠粉 penang fried rat noodle [ペナン風マカロニ]](https://w-foods.com/wp-content/uploads/2012/05/P1010894_1.jpg)
![炒檳城老鼠粉 penang fried rat noodle [ペナン風マカロニ]の麺](https://w-foods.com/wp-content/uploads/2012/05/P1010897_1-300x231.jpg)
!["炒檳城老鼠粉 penang fried rat noodle [ペナン風マカロニ]](https://w-foods.com/wp-content/uploads/2012/05/P1010892_1-300x231.jpg)





![ヤム・タクライ・クン・シアプ ยำตะไคร้กุ้งเสียบ [レモングラスとエビの和え物]](https://w-foods.com/wp-content/uploads/2012/05/P1020362wp-e1600483523891-320x180.jpg)




 できることなら値段を気にせず毎日買い物したい。成城石井。
できることなら値段を気にせず毎日買い物したい。成城石井。 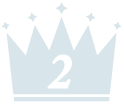 品揃えは圧倒的。カルディコーヒーファーム
品揃えは圧倒的。カルディコーヒーファーム  品揃えだけで行ったら軍を抜く!楽天市場!
品揃えだけで行ったら軍を抜く!楽天市場!